



↑藤枝市HPより
********************************************************************************
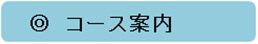
1・中山上バス停横の中山公園 2・県道81号線


1・ バス停は中山でも中山上バス停でも同じです。県道81号の入口にある中山公園にはトイレがあります。
2・ 双子山入口の材木屋を左に見ながら県道81号を不動峡に向けて進みます。
3・不動峡への分岐 4・城山(西砦・東砦)


3・ 山鼻地蔵のある橋を過ぎた所で不動峡への道に入る。正面に見える二つの山は南北朝時代には南朝方の二つの砦が
あったとされる城山です。交差点横の水防倉庫の滝之谷地区の見どころが案内されています。
4・ 民家のある旧道沿いに進むと前方に八坂神社の鎮守の森が見えてくるので、その手前を右折して橋を渡る。
八坂神社には無形民俗文化財の田遊びや神楽が伝承されています。
5・「柿の木坂の家」 6・不動峡への分岐


5・ お餅オープンカフェ 「柿の木坂の家」 の前を通り滝之谷川を渡る。
6・ 橋を渡り道なりに左折する。ここから水車村までは滝之谷川沿いの道を歩く。
7・滝ノ谷川沿の道 8・不動峡新滝温泉跡


7・ 「飛行機薬師」 を祀る龍雲寺を過ぎると道は薄暗い谷間の道になる。その入口には公園?のような広場がある。
8・ 滝之谷川に架かった立派な太鼓橋は、昭和16年まで営業していた “不動峡新滝温泉” の跡です。
不動峡に湧くラジウム鉱泉を利用し、橋の下には錦鯉を泳がせ舟を浮かべるなど贅を凝らした宿だったようです。
9・滝ノ谷川の渓谷 10・滝ノ谷川の渓谷


9・ 細い川だった滝之谷川も、上流は大きな岩が散乱した渓谷美を見せてくれます。
10・ 川沿いの細い道ですので車には注意しましょう。
11・不動明王堂 12・不動明王の磨崖仏


11・ 橋を渡ると摩崖仏をお祀りするお堂が見えてきます。
12・ 不動峡の磨崖仏は高さ10m幅7mもあり、不動明王の磨崖仏としては日本一の大きさです。
13・山の市 14・炭焼小屋跡


13・ 摩崖仏の少し上流には不動峡山の市があり、秋に行われる紅葉祭りは賑やかになります。
14・ 山の市を過ぎ水車村までは道は太くなります。水車村入口には炭焼小屋跡があります。
15・古民家 16・水車小屋跡


15・ 川向うにある古民家には吊橋を渡っていきます。
16・ 水車村と云っても壊れた水車小屋が一軒あるだけの集落です。
17・高尾山・菩提山分岐 18・地蔵の祠


17・ 古民家入口先を左に曲がり橋を渡ると道が分岐しています。右折する道は高尾山や笠張山ハイキングコースの下山口で
その標識が建っています。帰りはこの道を下ってきて、ここから中山バス停までは来た道を戻ることになります。
なお、笠張山への標識は建っていないが、笠張山の登山口はこの分岐を直進します。
18・ 景色も見えない農道を20分ほど行くと地蔵尊を祀った祠がある分岐に出る。林の中に入る道もあるが橋を渡って直進する。
19・菩提山入口&林道滝之谷峠 20・林 道


19・ 林道の傾斜が緩やかになると道の左側に菩提山入口の標識がある。さらにその少し先で林道は大久保へ道が分岐している。
“滝之谷峠” の標識は建っていないが、ここが林道の滝之谷峠で、ここも標識は無いが笠張山は林道を真っすぐ前進する。
20・ 稜線になった道は平坦で歩きやすくなったが、景色も見えなく花もない面白みのない道が続く。
21・滝之谷峠 22・滝之谷峠


21・ ようやく右に標識が見えてきて、かっての滝之谷峠に到着。
22・ 標識にはここから滝之谷へ下るようになっているが、踏み跡が薄いので一般の人は立入らない方が無難です。
笠張山への標識は無いが、さらに林道を前進します。
23・入口500mの標識 24・笠張山入口


23・ 初めて左側開けて高根山が見える場所があります。その先に 「笠張山登山口 この先500m」 の標識がある。
24・ この先500mの標識から約10分ほどで、右側のガードレールの先に 「⇦ 笠張山」 の標識がある入口に着く。
入口には、この標識が一つあるだけなので見落とさないように。
25・笹薮の道1 26・笹薮の道2 27・笹薮の道3



25~27・ 入口を入るとすぐ笹薮の急傾斜の道になる。道脇の笹を掴んで体を持ち上げる事もあるが、春先はまだタケノコの
状態で簡単に折れることもあるので注意してください。
凡そ30分も悪戦苦闘して上の笹薮が明るくなってくれば稜線はもうそこです。
28・尾根道入口 29・新道口分岐


28・ 笹薮の道が終り落葉で道が分かり難い所に出るが、上に向って10mも行けば林の奥に標識が見えてきます。
29・ 標識には今来た道を指して 「滝之谷峠」 。直進は 「笠張山」 となっているので直進します。
左折は 「笠張新道登口」 となっているが、この道は高尾山から来た道の登山口です。
30・尾根の道1 31・尾根の道2


30・ 笹薮の急傾斜の道を歩いて来たのので、平らな道がなんて快適な事か。これで景色が見えれば云う事はないのですが。
31・ 森の中で踏み跡が別れることもあるが先で合流します。気になるなら右の尾根に沿って歩けば間違いがありません。
32・笠張山山頂 33・山頂標識


32・ 景色も何も見えない笠張山山頂。藤枝のハイキングクラブの建てた立派な山名杭が立っています。標高698m
33・ 山頂にある標識は今きた道を 「菩提山」 、直進する道は 「高尾山」 となっていて滝之谷がありません。
笠張山コースを歩く人には少々不親切ですが、滝之谷は高尾山と書かれた直進する道を行きます。
34・展望地 35・展望地からの眺め


34・ 山頂から見ても前方が明るくなって見える所が展望地で、滝之谷へ行く道の途中にあります。
35・ このコースで唯一景色の見える場所です。昼飯はここの簡易ベンチに座って取るのがお進めです。
36・展望地横の下山道 37・高尾山分岐


36・ 滝之谷への道は展望地の横から下山道が始まります。入口の木には目印のテープが巻いてあります。
ここまではズート上りでしたが、ここからは下りの始まりでゴールまで基本的に下りです。
37・ 展望地から10分程で高尾山と滝之谷との分岐に出るので、そこを滝之谷方面に右折します。下りの直進は高尾山への道です。
38・作業道合流 39・作業道から山道へ


38・ 分岐を右折するとすぐに作業道に合流する。
39・ 作業道を2分も歩くと、林の中に入る標識をあるので見落とさないこと。
40・沢状にへこんだ道へ 41・私製の標識


40・ 作業道から分かれ、林の中を15分程下った辺りで、踏み跡が流されたような場所に出る。
前方にも薄い踏み跡らしきものが見えるが、そちらには行かずに沢状にへこんだ場所に向って左折する。
沢状の道を2分も下ると左側に踏み跡があるのでそこを進む。沢状の道は藪になる。
41・ 沢状にへこんだ道から出ると私製の標識があるが、草むらの中で見落とす可能性が高い。
42・標識の無い分岐 43・堰堤が見える


42・ 沢状の道を出てから10分ほど下ると、道が直進と左折に分岐した場所に出るが標識は無い。
ここは直進して沢に下る道を進む。
43・ 分岐を下りだすと沢の音が聞こえてきて右に堰堤が見える。
44・左右に沢が 45・左の沢を渡る


44・ 堰堤が見え道の周囲に竹林が見えてくると標識がある。更に少し下にも標識がある。
標識を見てホッとするが、突然前方が沢になった場所に出る。そこを左側の沢に下る。(簡単に下れます)
45・ 飛び石状の所を渡るが、渡った先で右に下る踏み跡があるが、そちらには行かないで真っすぐ上に登る踏み跡を行く。
大雨の後は沢を渡るときに靴を濡らしそうです。
46・上に登る 47・標識の先は林道


46・ 沢を渡ると直進方向の斜面に黒いパイプが上に延びているので、その横の踏み跡を登る。(簡単です)
47・ 斜面を登れば標識があり、その先は舗装された林道になる。
ここから先の道案内はYahooの地図で行います
48・ヤマメの郷跡 49・水車村合流


48・右の川を渡った所に廃業をしているヤマメの郷がある。
49・林道に合流して20分ほどで水車村に到着。合流した道は行きに歩いて来た道です。
ここからゴールまでは行きと同じ道ですので17から1を参照してください。
********************************************************************************

景 色 = ★ 景色は笠張山の展墓地からしか見えない。
登山道 = ★★ 笠張山の笹薮の上りや沢の渡渉は雨の後では苦労しそうです。
道 標 = ★★ 行きの水車小屋や林道の滝之谷峠には標識が無い。また笠張山山頂の標識には滝之谷の表示がない。
見 所 = ★★ 滝之谷の摩崖仏があるぐらい。
総 評 = ★ 景色は見えないし長い舗装路歩き、しかも中山から水車村までは同じ舗装路を歩かなければならない。
帰りのバスの便も悪いので水車村まで車を利用した方が良いでしょう。
高尾山コースと笠張山コースを合体した方が面白味のあるコースになります。(工事中)
難易度見直し = 中級認定そのままで良い。


※ガイドブックは滝之谷峠から笠張山山頂までの所要時間を20分としているが、林道の笠張山入口からでも
30分はかかるので、例え手前にある旧滝之谷峠からとしても20分はとても無理です。
新しいガイドブックの表記にも
「水車小屋から林道高尾線を北に進み、滝之谷峠に差し掛かったところで北東へと進路を変え、、暫くすると
笠張山の山頂です。」 と、いとも簡単に書かれています。何処かと別の場所と勘違いしているようです。
********************************************************************************
ページトップへ戻る 藤枝ハイキングへ戻る メインメニューに戻る